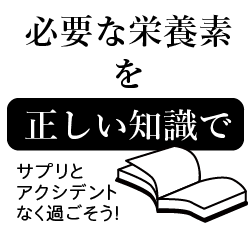健康志向が高まるなかで、注目を集めているのが「食物繊維」です。便通を整える成分というイメージが強いものの、その働きはそれだけにとどまりません。腸内環境の改善、血糖値やコレステロール値の上昇抑制、さらには生活習慣病の予防など、体の内側から健康を支える多面的な効果が明らかになっています。
しかし、日本人の多くは推奨量に達しておらず、意識して摂取しなければなりません。本記事では、食物繊維の種類や機能、含有食品、日常生活への取り入れ方、そして注意点までを幅広く解説し、毎日の食事をより健康的に整えるための実践的なヒントを紹介しまうs。
食物繊維とは?
食物繊維とは、人の消化酵素で消化されず、小腸を通過して大腸まで到達する成分です。主な働きには、次のようなものがあります。
- 噛む回数を増やし、満腹感を向上させる
- 糖・脂質の吸収をゆるやかにし、 血糖値・コレステロール値の上昇抑制
- 便の量を増やし、腸のぜん動運動を促す
このように、食物繊維はさまざまな働きがあり、最近では5大栄養素に続く、6つ目の栄養素として注目を集めています。しかし、日本人は食物繊維の摂取量が年々低下しており、1950年の摂取量と比較して6g以上も摂取量が減っていると推計する厚生労働省のデータもあります。健康的な生活を目指すためには、食物繊維の積極的な摂取が欠かせません。
参考:厚生労働省 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~ 食物繊維
食物繊維の種類
食物繊維は、その性質によって大きく2つの種類に分けられます。まずは、水溶性食物繊維です。水溶性食物繊維は、その名の通り水に溶けやすく、糖や脂質の吸収をゆるやかにする働きがあります。また、血糖値やコレステロールの上昇抑制にもつながるのが特徴です。
不溶性食物繊維は水に溶けにくく、腸に運ばれるとぜん動運動を促します。便のかさを増す働きもあるため、便秘の予防には欠かせない物質です。
また、近年注目されている食物繊維に、「発酵性食物繊維」と呼ばれる物質があります。これは腸内の善玉菌をエサにして働き、腸内環境を整える役割があります。
これらのうちどれかを摂取すればよいわけではなく、バランスよく摂取するよう心がけるのが大切です。
食物繊維を多く含む食材を知ろう
食物繊維は、食材によってほとんど含まれていないものもあれば、豊富に含まれているものもあります。ここでは、豊富に含まれている食材をご紹介します。
- 穀類…玄米、麦飯、胚芽米
- 豆類…大豆、あずき、納豆、おから
- 芋類…こんにゃく、さつまいも、サトイモ
- 野菜…ごぼう、ふき、キャベツ、白菜
- きのこ・海藻類…しいたけ、しめじ、わかめ、もずく
- 果物…みかん、グレープフルーツ
食材によっては、生で摂取するよりも、調理したものの方が食物繊維の含有量が増えるケースもあります。たとえば、大根はそのまま食べるよりも、切り干し大根の方が食物繊維が豊富です。野菜といえば新鮮なものを食べる方が栄養素が豊富に含まれているイメージですが、どの調理方法であればいいか、あらかじめチェックしておくと良いでしょう。
食物繊維を日常に取り入れるポイント
食物繊維が豊富に含まれている食材が分かったら、次は日常生活に取り入れるポイントを押さえましょう。まずは、炭水化物ばかりになってしまう方は、玄米や麦ごはん、ライ麦パンなど食物繊維が豊富に含まれる穀類に変更してみてください。付け合わせはごぼうや芋、こんにゃくなど噛み応えのある食材を加えると、摂取量が増やせるほか満腹感を得られます。
食事の種類を増やすのが難しければ、根菜を皮ごと食べたり、種も残さず調理したりすると、摂取量を自然と高められます。もし摂取量が低い日があっても、1週間のトータルでバランスが取れれば問題ありません。ハードルを上げ過ぎずに、できることに取り組むのが大切です。
食物繊維を摂取する注意点
食物繊維は過度に摂取すると、問題が生じる可能性もあります。たとえば、必要以上に摂取すると、鉄・カルシウム・マグネシウムなどのミネラルの吸収を阻害してしまうことも。不溶性食物繊維を取りすぎると、便が柔らかくなって下痢をするケースも見られます。
また、食物繊維が豊富に含まれているからと果物を食べ過ぎると、糖分が過多になり、美容や健康に悪影響を及ぼしかねません。何事も適量を意識しつつ、バランスよく摂取することがポイントです。
まとめ
食物繊維は、腸内環境を整えるだけでなく、血糖値や脂質のコントロール、満腹感の維持、肌や免疫のサポートなど、多面的に健康を支える成分です。
重要なのは、水溶性・不溶性をバランスよく取り入れ、過不足なく続けること。玄米や雑穀、豆類、野菜、海藻、きのこ類などを日々の食事に少しずつ加えることで、無理なく摂取量を増やせます。過剰摂取や偏りに注意しながら、「適量・多様性・継続」を意識することがポイントです。
日常の小さな工夫が、腸から全身の健康へとつながる第一歩となるでしょう。